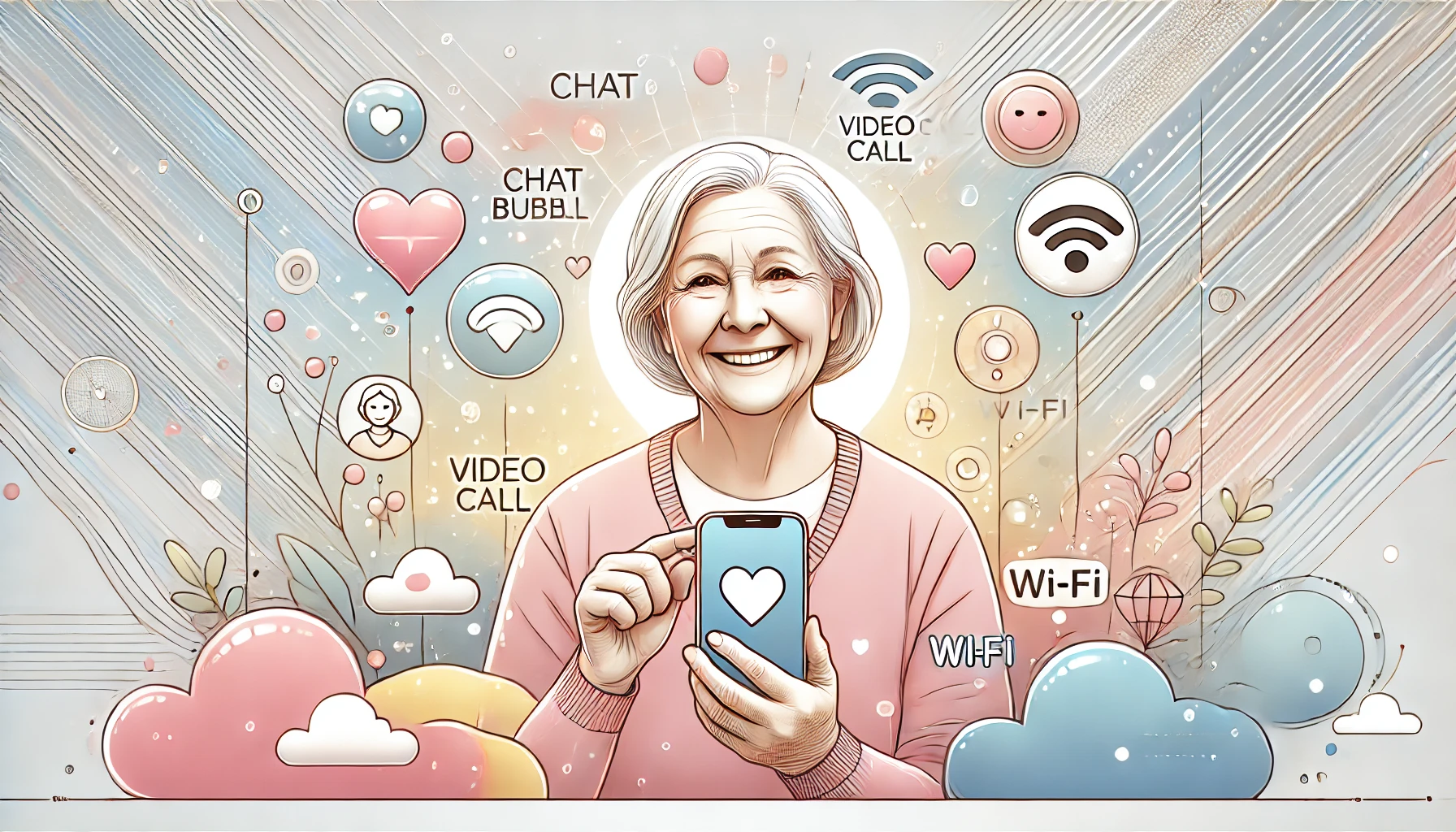- シニア世代のデジタルデビューは不安や戸惑いがあっても、健康管理、日常の利便性向上、家族・友人とのコミュニケーション拡大など、生活を豊かにする大きなメリットがある
- デジタル活用には安全対策が不可欠で、パスワード管理の徹底や詐欺メールの見分け方、個人情報の守り方など、セキュリティの基本知識を身につけることが重要
- 無理せず自分のペースで学び、自治体や携帯キャリアのスマホ教室、家族のサポートなど継続的な学習環境を活用することがデジタル活用成功の鍵となる


デジタルデビューの意義とメリット
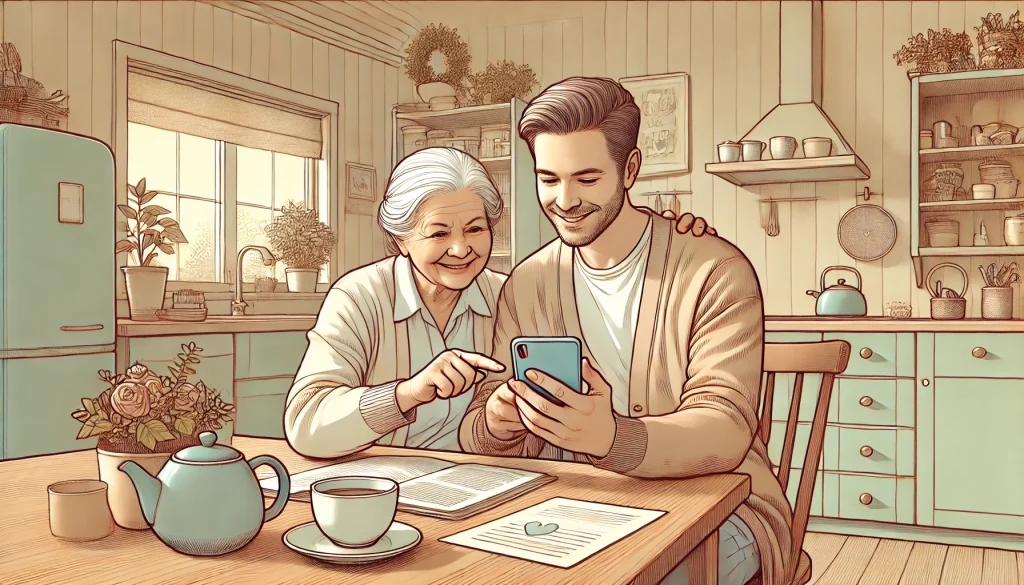
デジタルデビューとは、これまでデジタル機器やインターネットをあまり使ってこなかった方が、新たにスマートフォンやタブレットなどを使い始めることです。特にシニア世代にとって、長年親しんだガラケー(従来型携帯電話)からスマートフォンへの移行や、インターネットサービスの活用は大きな変化となります。
デジタルデバイドの現状と課題
デジタルデバイドとは、情報通信技術を使いこなせる人と使いこなせない人の間に生じる格差のことです。総務省の令和5年版情報通信白書によると、60代のスマートフォン保有率は約85%、70代では約65%、80代以上では約40%と年齢が上がるにつれて低下しています。
主な課題としては、操作方法の複雑さへの不安、セキュリティや詐欺への懸念、学習機会や相談先の不足、身体機能の変化(視力・聴力・指先の感覚など)への対応が挙げられます。
シニア世代が得られる生活の変化
デジタル機器やインターネットを活用することで、シニア世代の生活はより豊かになります。健康管理アプリで日々の健康状態を記録・管理したり、緊急時の連絡手段の確保、防災情報をリアルタイムで受信するなど、健康・安全面でのメリットがあります。
また、オンラインショッピングで重い荷物を持ち運ぶ必要がなくなる、銀行窓口に行かなくても振込や残高確認ができる、タクシー配車や食事の宅配など生活サービスの簡単な注文ができるといった生活の利便性向上も期待できます。
さらに、離れて暮らす家族や友人とビデオ通話で顔を見ながら会話したり、SNSを通じて趣味の仲間との交流、地域の情報やイベント参加の機会増加など、コミュニケーションの広がりも実感できるでしょう。
自治体・行政の支援活動
全国の自治体では、シニア世代のデジタル活用を支援するさまざまな取り組みが行われています。例えば渋谷区では「シブヤ・スマホ活用大作戦」を実施し、65歳以上の区民に対してスマートフォンの貸与や講習会を行っています。
少人数制の実践型講座(LINE、メール、地図アプリなど実用的な内容)、個別相談会の定期開催(マンツーマンでの質問対応)、区内のIT企業と連携した継続的なサポート体制が特徴です。参加者からは「同世代の方と一緒に学べて安心できた」「繰り返し質問できる環境がありがたい」との声が多く寄せられています。
その他にも、総務省「デジタル活用支援推進事業」による全国各地でのスマホ教室、東京都「シニアITサポート事業」による出張講座、大阪市「シニアICTサポーター制度」によるシニア同士の学び合いなど、さまざまな支援が行われています。
スマートフォン・インターネットの基本と活用法

スマートフォンの選び方と基本設定
スマートフォン選びでは、文字が読みやすい大きめの画面(5.5インチ以上)、長時間持っても疲れない軽量なもの(180g前後)、最低でも一日使えるバッテリー容量、「かんたんモード」「シニアモード」などの搭載、店舗での相談サービスや保証内容などのアフターサポートが重要なポイントです。各キャリアの「シニア向けスマホ」や「かんたんスマホ」シリーズ、ドコモの「らくらくスマートフォン」、auの「かんたんスマホ」、ソフトバンクの「シンプルスマホ」などが代表的な機種となっています。
初期設定では、文字サイズの調整や画面の明るさ調整、必要なアプリのみ通知をオンにする設定、バッテリーを長持ちさせる省電力設定、万が一の際に役立つ緊急連絡先の登録などを行うとよいでしょう。これらの設定は「設定」アプリから簡単に変更できます。
日常で役立つアプリの活用法
LINEでは、トーク(個人・グループ)でのメッセージのやり取り、スタンプ送信、写真共有などが基本操作です。家族グループの作成は「友だち追加」から「グループ作成」を選ぶことで簡単に実現できます。ビデオ通話はトーク画面右上のビデオカメラアイコンをタップするだけで開始できます。
メールは、アカウント追加や署名設定などの基本設定を行い、宛先入力、件名、本文、送信などの基本操作を覚えましょう。写真や文書などの添付ファイルの送信方法も覚えておくと便利です。
カメラの基本操作には、写真撮影、ビデオ撮影の切り替え、保存した写真の確認方法、LINE、メールでの写真共有方法などがあります。撮影した思い出の写真を家族や友人と共有することで、コミュニケーションが広がります。
インターネット検索と情報活用のヒント
検索エンジン(Google、Yahoo!など)を使った情報収集では、複数の言葉を組み合わせたキーワード検索が効果的です。信頼できる情報源の見分け方として、政府機関や公的機関のサイト(.go.jpドメイン)を優先することをお勧めします。よく見るサイトはブックマーク(お気に入り)に登録しておくと、次回から簡単にアクセスできます。
また、スマホに話しかけるだけで操作できる音声アシスタント(Siri、Googleアシスタント)も便利です。「明日の天気は?」「アラームを設定して」「〇〇さんに電話して」などのコマンドを覚えておくと、手が塞がっているときや文字入力が面倒な場合に役立ちます。音声入力でのメッセージ作成や、拡大鏡機能、読み上げ機能なども、シニアには特に便利な機能です。
安心・安全にデジタルを楽しむための対策

セキュリティ管理の基本知識
パスワード管理では、長さ(12文字以上)と複雑さ(大文字・小文字・数字・記号の組み合わせ)を持つ安全なパスワードの作成が重要です。パスワードを使い回さないことも大切なポイントです。パスワード管理アプリを活用し、メモ帳に書くのはなるべく避けましょう。また、二段階認証を設定すると、さらにセキュリティが向上します。
詐欺メールの特徴としては、差出人アドレスの不自然さ、誤字脱字、急かす文面などがあります。代表的な詐欺の手口には、「料金未払いのため法的手続きに」などと脅す架空請求、「アカウントが停止されます」などと焦らせるフィッシング、家族や知人を装った「急にお金が必要」などのなりすましがあります。身に覚えのないURLやファイルは開かない、少しでも怪しいと思ったら別の連絡手段で確認するなどの注意が必要です。
家族との安全な情報共有と対策
家族共有設定(Apple「ファミリー共有」、Google「ファミリーリンク」など)を活用すると、アプリやコンテンツを家族で共有できる便利な機能があります。位置情報共有の設定と解除方法も覚えておくと、互いの安全確認に役立ちます。ただし、写真や個人情報をSNSで共有する際には、プライバシーに関わる情報が含まれていないか注意しましょう。トラブル時に家族がリモートでサポートできる設定も便利です。
ソーシャルエンジニアリング対策として、個人情報を電話やメールで簡単に教えない、「今だけ」「特別」などのセールストークに惑わされない、公的機関を装った連絡に対する確認方法を知っておく、不審な連絡があった場合の相談先(消費者ホットライン188など)を確認しておくことが大切です。
生活を豊かにするデジタル活用術

健康管理と生活便利ツール
デジタル機器は健康管理にも役立ちます。歩数計アプリで毎日の運動量を記録したり、血圧や体重を記録する健康管理アプリ、食事の栄養バランスをチェックするアプリ、脳トレゲームで認知機能を楽しく維持するなど、様々な活用法があります。「みんなの認知症予防ゲーム 脳トレ」「歩数計 歩いてコイン」「健康第一」(血圧・体重記録)などのアプリが人気です。
オンラインショッピングでは、Amazonや楽天市場などの基本的な使い方、商品の検索方法、レビューの見方、注文手順を覚えておくと便利です。キャッシュレス決済には、クレジットカード、電子マネー(Suica、PASMO、nanaco、WAONなど)、QRコード決済(PayPay、LINE Pay、楽天ペイなど)があり、それぞれの特徴を理解して使い分けるとよいでしょう。安全な決済のためには、不正利用防止対策も忘れずに行いましょう。
コミュニケーションと地域連携
LINE、Facebook、Instagramなどの主要SNSを活用すれば、離れて暮らす家族や友人とのコミュニケーションが広がります。ビデオ通話アプリ(Zoom、LINE、Facetimeなど)を使えば、顔を見ながら会話を楽しむことができます。オンライン上でのコミュニケーションマナーやプライバシー設定の確認方法も押さえておきましょう。
防災面では、気象庁や自治体の防災アプリ、避難所マップ、災害用伝言板などの災害時に役立つアプリ、地域の情報を得るためのアプリやサイト、緊急速報メールの設定確認などが役立ちます。多くの自治体では、LINEの公式アカウントを通じて防災情報を配信しています。
東京都豊島区ではLINE公式アカウントで防災情報を配信し、定期的に防災訓練のメッセージを送信、神戸市ではLINE公式アカウントで地震や豪雨の際の避難所情報をリアルタイムで提供するなどの取り組みが行われています。
また、地域のシニアサロンやサークル情報の入手、オンラインコミュニティへの参加、地域限定の情報交換アプリ(ジモティーなど)の活用、自治体のデジタル活用支援講座の探し方など、地域とのつながりを深める方法もデジタルを通じて広がっていきます。
継続的な学びとサポート活用
デジタルスキルは継続的に学ぶことが大切です。各携帯キャリアのスマホ教室(ドコモ、au、ソフトバンクなど)、自治体主催の無料講座、民間のシニア向けパソコン・スマホ教室などを活用しましょう。受講する際のポイントとして、少人数制か個別指導か、実機を使った実践形式か、質問や復習の機会があるかなどをチェックするとよいでしょう。
YouTubeでのスマホ操作解説動画の視聴、オンライン学習サイト(Schoo、Udemy、JAYEDGE「シニアのためのスマホ講座」など)の活用、各キャリアの公式サポートサイトの参照など、自宅でも学べる環境が整っています。操作に関する疑問を検索するコツも身につけていくと良いでしょう。
困ったときには、各携帯会社のユーザーサポート窓口、メーカーのサポートセンター、総務省「デジタル活用支援」相談窓口、消費者ホットライン(詐欺・トラブル相談)などを活用できます。電話をかける前に、契約者情報や質問内容のメモを準備しておくと、スムーズに相談できます。
地域の公民館やコミュニティセンター、シニア同士の学び合いの場(シニアITサポーター制度など)、図書館でのデジタル講座、学生ボランティアによるサポートなど、世代間交流の場も活用しましょう。
トラブル対応とFAQ

トラブル時の基本的な対処法
デジタル機器の操作に迷ったら、「戻る」ボタンや「ホーム」ボタンで一度リセットすることで、問題が解決することがあります。アプリが動かなくなったら、電源の長押しから再起動を選択しましょう。
その他、誤って削除したデータの復元方法、パスワードを忘れた場合のリセット方法、スマホを紛失した場合の対処法(リモートロック、位置確認など)、バッテリーの消耗が早い場合の対処法(バックグラウンドアプリの確認など)、アプリの支払いトラブルへの対応(キャリア決済の確認方法など)について知っておくと安心です。
よくある質問と回答
まとめ:一歩ずつ進めるデジタルライフ
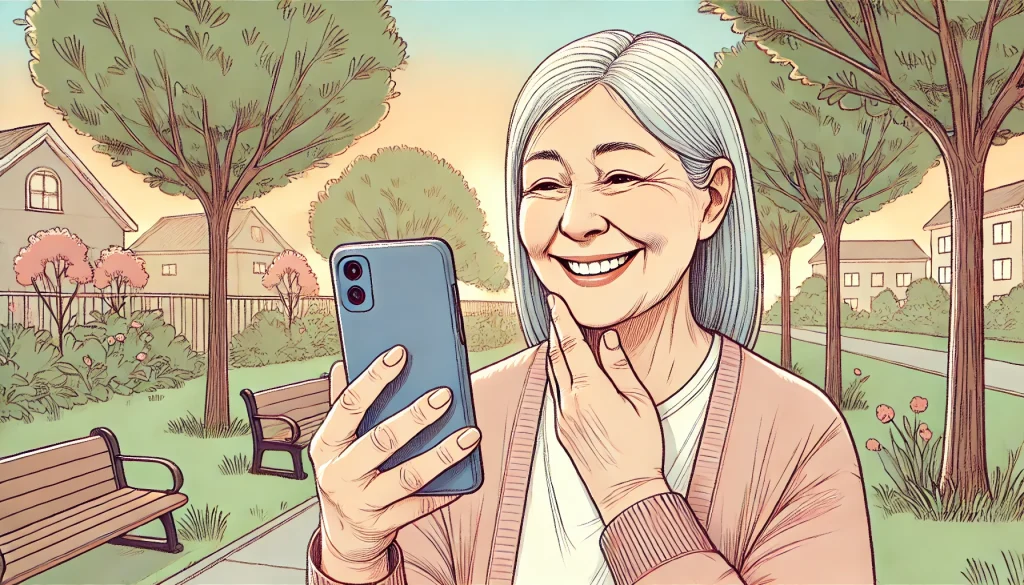
デジタルデビューは、最初は不安や戸惑いがあっても、少しずつ慣れていくことで大きな可能性が広がります。スマートフォンやインターネットは、シニア世代の生活をより便利で豊かにする強力なツールです。
大切なのは、無理せず自分のペースで学び、分からないことは遠慮なく質問し、セキュリティに注意しながら楽しく活用していくことです。家族や地域の支援を受けながら、新しい技術とともに成長していく姿勢が、豊かなシニアライフにつながります。
成功の秘訣は、自分の生活に役立つ機能から少しずつ取り入れていくこと、同世代の仲間と一緒に学び合う機会を持つこと、定期的に学習の場に参加することにあります。デジタル活用は目的ではなく、より充実した生活を送るための手段です。健康管理、家族とのコミュニケーション、趣味の広がり、地域との交流など、あなたにとって価値のある活用法を見つけていきましょう。
一歩ずつのチャレンジが、新たな発見や喜びにつながります。この記事が、あなたのデジタルデビューの一助となれば幸いです。